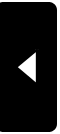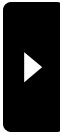スポンサーサイト
鹿児島弁アンケート結果発表!
2016年07月30日
7月16日(土)~17日(日)に開催されたかごしま弁フェスティバルにおいて、GAiGOのブースで実施した鹿児島弁アンケートの結果を発表します!



今回は「んだもしたん」「やっせん」「わっぜ」「だれた」「だからよ」という5つの言葉を取り上げて、「よく使う鹿児島弁」と「外国人に教えたい鹿児島弁」という2つのテーマで、ブースの入り口付近に掲示した表にシールを貼ってもらう形でアンケートを実施しました。
ある程度予想はしていましたが、イベントの来場者は60歳以上の年配の方が一番多いようでした。ただ、GAiGOのブースには親子連れや大学生などのほか、外国人のかたも数組遊びに来てくれました。また、会場では7月3日(日)に鹿児島外語学院(GAiGO)が主催した「英語落語ワークショップ&講演会」に参加しました、とても楽しかったです、と複数の方から声を掛けられました。
言葉別の集計では、「よく使う鹿児島弁」と「外国人に教えたい鹿児島弁」がほぼ逆の結果になるという興味深いデータが得られました。
また、それぞれ年代別にも大きな違いがみられました。
「だからよ」という表現は、相手が言ったことに対して「そう、そう!」という共感を示す表現で、若者の間では広く使われていますが、年配の方からは「鹿児島弁ではない」と指摘をする方もいらっしゃったようです。しかし、言葉というのは常に変化するもの。昔から使われている表現ではないにしても、鹿児島人が県外に出て使用すると「だから何?」という反応をされて初めて鹿児島独特の表現だったんだと気付く表現なのです。その意味ではりっぱな鹿児島弁といえるでしょう。
英語専門学校がかごしま弁(方言)という、一見関係のなさそうなテーマに挑んだ今回のイベント。第1回目ということで、不確定要素が多く、生徒たちも戸惑っていましたが、「観光資源の一つとしての鹿児島弁を外国人に発信する」というテーマのもと、徐々に理解が深まり、準備にも熱が入っていきました。実際には年配の方が多いこともあり、英語というだけで拒否反応を示すかたも多くいらしゃいましたが、一方で「茶碗むしの歌」の英訳や英語バージョンが大人気で、一定の成果は得られたと感じました。終了後の生徒のレポートでは「普段意識することのなかった鹿児島弁に触れるいい機会になった」という感想が多くみられました。



異文化カレッジをお手伝いしました。
2016年06月20日
6月19日(日)、鹿児島市教育総合センターで(公財)鹿児島市国際交流財団(KIEX)が主催する異文化カレッジが実施されました。
異文化カレッジは、鹿児島市民に英語の授業や、異文化についての授業を提供するものです。鹿児島外語学院(GAiGO)でMedia StudiesやPresentationのクラスを担当するJim先生も講師を務め、生徒は受付などの手伝いと、先生のアシスタントを務めました。


異文化カレッジは、鹿児島市民に英語の授業や、異文化についての授業を提供するものです。鹿児島外語学院(GAiGO)でMedia StudiesやPresentationのクラスを担当するJim先生も講師を務め、生徒は受付などの手伝いと、先生のアシスタントを務めました。
Jim先生は、初心者でも簡単な英語で自己紹介をする練習から入り、最後は「防災」をテーマに、参加者同士でコミュニケーションをとる練習をしました。その後も、生徒はほかの参加者と一緒に授業に参加しました。
GAiGOの生徒も、いつもとは違う授業に刺激を受けたのではないでしょうか。
さて、次のイベントは7月3日(日)にGAiGOがKIEXと共催する英語落語ワークショップ&講演会です。前座で出演する生徒は現在、毎日落語の練習に取り組んでいます。まだ若干席に余裕がありますので、この機会に英語への新たな切り口として参加してみませんか。お申し込みはこちらよりお願いします。


Hearty Party
2016年04月24日
4月24日(日)、鹿児島中央駅前のキャンセビル8階体育館にて、(公財)鹿児島市国際交流財団(KIEX)が主催する「春の新入外国人歓迎交流会 ハーティパーティ」が開催されました。鹿児島外語学院(GAiGO)はKIEXの賛助団体であり、手嶋学長は理事を務めています。

入り口の看板

今年鹿児島に来られた外国人のみなさん

じゃんけん列車ゲーム

世界各国のお菓子

GAiGOがお手伝いした茶道体験ブース

お菓子の説明をする生徒
GAiGOのメンバーは10時に集合し、準備にあたりました。
イベントは13:30に開始。全員によるゲームで和んだ後、日本や各国の文化体験をしていただきました。
GAiGOは茶道体験ブースのお手伝いをさせていただきました。
学院で月に1回ある茶道クラスでお作法を学んできた国際科2年生は、手慣れた手つきでお点前のお手伝い。
ほかのメンバーはお菓子やお茶を運んで、お茶の飲み方などを英語で説明しました。
最後は、みんなが輪になっておはら節を踊りました。
外国人留学生の皆さん、鹿児島を存分に楽しんでくださいね。






南太平洋の大学生と交流しました。
2015年12月14日
12月14日(月)の午後、南太平洋に浮かぶフィジーをはじめとしたバヌアツ・マーシャル諸島・ソロモン諸島などで構成される国・大洋州の大学生25名+引率2名を学院にお迎えして、文化交流を行いました。鹿児島大学に在学する大洋州出身の留学生ら4名も参加しました。鹿児島ではめったに同郷の人に会う機会がないため、交流を楽しみにしてくれていました。

ポスターの裏紙を使った手作りの歓迎横断幕

大洋州の大学生によるダンスの披露

GAiGOの前で記念撮影

GAiGO生による落語の説明

このグループは紙鉄砲づくりと「ハイジャック」の小噺

ここは紙箱と「ホームズジョーク」の小噺

ここは手裏剣と「名画鑑賞」の小噺

ここは兜・刀と「ハンタージョーク」の小噺

ここはスリッパと「葬式」の小噺

最後に各グループのプレゼンテーション

このグループは小噺を劇方式で熱演^0^右の人は犬役です。

最後に学院オリジナルの校歌GAiGOとMOTTAINAIを合唱
その後、訪問団の代表からのお礼のあいさつがあり、GAiGOからは記念に全員にパンフレットをプレゼント。手嶋学長の「来年の入学待ってます。」という冗談にも笑いが起きました。

記念撮影

名残惜しそうにそれぞれ記念撮影
この事業は、外務省の「21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYSプログラム)」において公益法人青年海外協力協会が主催する短期招聘事業で、鹿屋市にある鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター(カピックセンター)が受け入れ先となっています。今回の訪問団は「日本語・日本文化コース」で、鹿児島での滞在中、鹿屋体育大学での剣道・柔道見学や小学校の課外活動への参加、ホームステイなどを経て、最後にメインの学校交流の相手としてGAiGOを選んでいただきました。
午後2時前に訪問団が到着。せっかくなので、生徒は全員浴衣 でお迎えしました。
でお迎えしました。
 でお迎えしました。
でお迎えしました。最初に予定していたダンスには広いスペースが必要ということで、鹿児島大学のフィジー人留学生が管理人に掛け合い、留学生会館の交流スペースを貸してもらうことができました。


それから学院に移動すると、まずはGAiGOの目玉でもある英語による落語の紹介。
パワーポイントを使いながら落語の歴史や演じ方などを解説した後、8月8日に前期末英語発表会として実施した英語落語寄席で国際科1年生の大迫空海子さんが披露した「寿限無(じゅげむ)」をビデオで鑑賞してもらいました。長い名前が何度も繰り返されるというのが笑いどころの一つですが、みんな終始大笑い やはり日本の伝統の中で培われた話芸は世界共通でウケるようです
やはり日本の伝統の中で培われた話芸は世界共通でウケるようです
 やはり日本の伝統の中で培われた話芸は世界共通でウケるようです
やはり日本の伝統の中で培われた話芸は世界共通でウケるようです


その後、グループに分かれてワークショップへ。
その後再び集合し、各グループが行ったアクティビティについての簡単なプレゼンと、小噺の披露をしてもらいました。
落語はひとりで演じる話芸ですが、練習する中で盛り上がり、多くのグループは複数人が劇方式で演じました。
ネタの面白さもさることながら、みなが楽しそうに熱演し、会場は大笑いと拍手喝采の嵐でした








学院創設者である故・手嶋八洲男(てしまやすお)作詞作曲による校歌GAiGOと、同じくオリジナルのMOTTAINAIを生演奏で披露。
手嶋学長とPatrick先生に加えて、国際科1年生のFumiyoとNanaがギター伴奏をし、MOTTAINAIでは英語科のNatsukiがボンゴを叩くというのがお決まりになっています。MOTTAINAIは、2つのコードのみで構成されるレゲエ調の曲で、歌詞もリードに続いて繰り返すので、練習しなくてもすぐに歌えてしまうという優れものです。でも、1回目はリハーサルということで、2回歌いました。2回目はさらに完成度が高まり、ボンゴも訪問団の一人が叩くなど大盛り上がりでした


最後に訪問団からお別れの歌が披露され、全プログラムが予定通りの時間で無事に終了。
全員での記念撮影後は、各々が自分のスマホで色んな人と記念撮影をし、ブレスレットなどのお土産もいただきました。
今後も継続して交流を深めていけることを願います。GAiGO生も今後大洋州に行く楽しみができましたね



通訳ガイド実地研修@仙厳園
2015年12月03日
12月2日(水)の午前中、鹿児島市の仙厳園(せんがんえん)において、日本の文化クラスと通訳クラス合同による通訳ガイド実地研修を実施しました。鹿児島外語学院(GAiGO)では、年間を通じて非常に多くの実地研修や国際交流イベントがあり、さらに実際に生徒が外国人観光客のためのボランティア通訳ガイドをする機会もあります。この研修に向けて、通訳クラスを中心に仙厳園について学習してきました。
仙厳園は、薩摩藩の19代藩主・島津光久(しまづみつひさ)によって築かれた別邸です。錦江湾や桜島を庭園の景観に取り入れた雄大な景色が最大の魅力です。さらに今年世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の鹿児島県内の構成資産「集成館の先駆的工場群」(旧集成館、関吉の疎水溝、寺山炭窯跡)はこの磯地区にあり、そのうち「旧集成館反射炉跡」は仙厳園の敷地内にあります。そのため、今後は海外からの観光客もますます増加することが予想されます。

スーツ着用、資料とバインダーは必須

日本唯一の猫神社

磯名物の両棒(ジャンボ)餅

尚古集成館

旧鹿児島紡績所技術館(異人館)

世界遺産を背負ってます!

当日は午前9時半現地集合。仙厳園を運営する島津興業の営業部長の方がわざわざご挨拶に来てくださり、世界文化遺産登録の決め手となった日本の近代化の特異性を解説してくださいました。ポイントは以下の2点です。
①西欧の知識と日本の技術の融合
鎖国体制下で西欧から設備機械を輸入することも、専門家を招くことができない中、書物から得られる限られた知識を、日本の在来の技術と融合させて造り上げた
②軍備の強化よりも、人々に豊かな暮らしを
軍事力強化だけでなく、人々に豊かな暮らしを保証して人の和を生み出す。それが日本を守る城となるという考えに基づく「富国強兵」を唱え、民需産業の育成や社会基盤の整備にも力を注いだ
そして園内に入ると、各ポイントで担当の生徒が調べてきた情報をもとに説明をしました。さらに手嶋学長と島田暁美先生から補足情報や解説、ガイドとしての心得やマナーなどが伝授されました。
世界遺産登録が決定したこともあり、園内には以前よりもパネル等の設備がさらに充実しており、入り口では、パンフレットをなぞると音声ガイドが流れるペン型の機械の貸し出し(500円)までありました。ハイテクですね;)
また、隣接する尚古集成館と、旧鹿児島紡績所技術館(異人館) も見学しました。
県外出身の生徒もいますが、県内で生まれ育った生徒でも、鹿児島の歴史や文化について知らない部分が多いのが事実です。自分のルーツである日本や地域のことを自分の言葉で、そして英語で語れる真の「国際人」を目指して頑張りましょう。